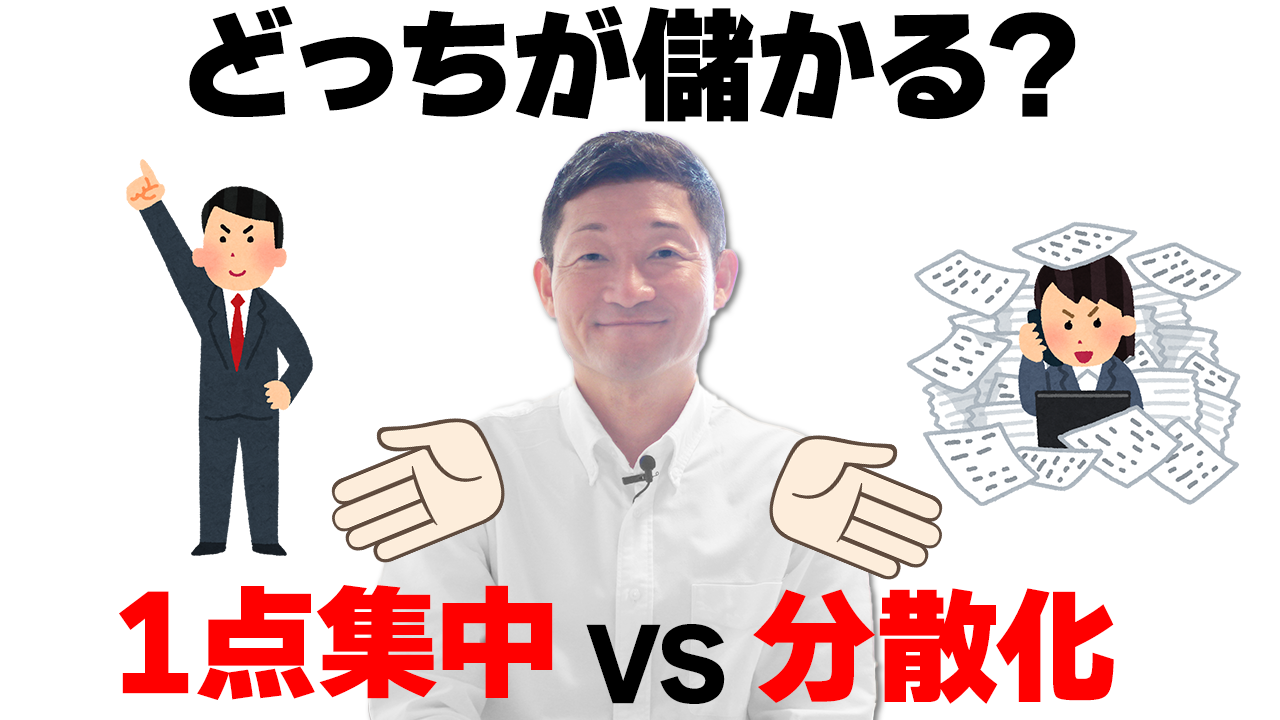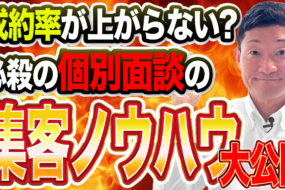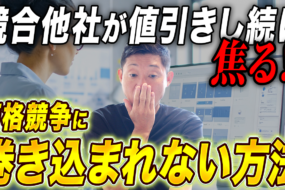ビジネスは「一点突破」か「分散戦略」か?起業で悩む問題に答えてみた。2025年トレンドは●●です。
 日本河野竜夫
日本河野竜夫目次
『1点集中するか?
分散してリスクヘッジするか?』
ビジネスを大きくしたい場合、
このような2つの大きな論調があります。
「ビジネスは1点集中せよ、
そうしないと全部が中途半端でどれも成果が出ない。」
というものと、
「市場の変化に耐えれるように複数の事業を行い
リスクヘッジをしつつ収益を最大化するべきだ。」
というもの。
たぶん一般的には
「いろいろ手を出したけど全部中途半端でものになってない。」
パターンの方が多いと思います。
なので、やはりフォーカス一点集中がいいのでは?
という意見の人も多いと思います。
実際ビジネス書でも、
「フォーカス」「ワンシングス」などなど、
多方面に手をだすことの愚かさを述べているものも多いですよね。
僕も起業当初はいろいろやりましたが、
成果が出たのは海外在住者のコンサルへ集中してからだし、
それが正しいなと思っていました。
ただ17年経過し、
いろんなケースを経験してきました。
また時代も変わりました。
そこでわかったのは、
そんな単純でもないなということなんです。
つまり、
フォーカスするほうがいい場合と、
分散する方がいい場合が両方あるんです。
正解が混在していると言ってもいいかもしれません。
ということで今日は、
結構意見のかかれる1点集中すべきか?分散すべきか?
について僕の考えを話します。
動画で見る|ビジネスは「一点突破」か「分散戦略」か?
文章バージョン続き|ビジネスは「一点突破」か「分散戦略」か?
■なぜフォーカス(1点集中)すべきなのか?
まずフォーカス(1点集中)の話から。
大前提として、フォーカス(一点集中)といった戦略論は、
究極的には「資源(リソース)の使い方」の話から来ていると思うわけです。
どういうことかというと、僕たちがゼロからビジネスをやる場合、
時間、資金、人的能力といったリソースが大手(強者)と比べて圧倒的に少ないからです。
だから、たったひとつの市場や顧客層にリソースを一点に高密度で投入し、
「局地戦」で戦えるようにしようってことですね。
また、その人に強みがあるとしても、
その強みが活かせる分野はそれほど多くないだろうし、
そもそも人間一人の集中力は多方面に分散させるほど高くないので分散しただけで、
ただでさえ少ないリソースの密度も下がってしまうんだろうということですね。
これはランチェスター戦略の基本でもあります。
なので、起業当初にしても、別の収入の柱を作りたい時にせよ、
何かのビジネスをはじめるときには、
弱者であるかぎり「一点集中」を必ずするべきだってことになります。
Aの事業を準備しながら、
Bも始めるみたいな並列処理は避けるべきってことになります。
「1個とりかかったなら、それだけをやるべき。」
ってことはすべての根底にあると思います。
■それでも分散しなければならない?
そうなると「やっぱ1点集中するべきだ」で話が終わってしまうのですが、
そう単純でもありません。
ここまで話した「1点集中せよ」の理由には、
限られた資源を集中投下せよってこと以外に、
「効率的に成果がでるものに集中せよ。」って意味もあるんです。
言い換えれば、
「楽に成果がでることに集中したほうが良い、」ってことです。
「1点集中することで成果はでやすくなる」ものの、
1点集中が「楽に成果を出す」ことと
イコールではないってことなんです。
いくつかのケースを説明しますね。
1、ビジネスはやってみないとわからない。
ビジネスは集中したかどうかの前に、
それが’売れるかどうか?がマーケットで決まります。
極端な話、1点集中してがっつり展開したサービスより、
片手間に短時間でリリースしたもののほうが利益が短期間ででることすらあるわけです。
そういう意味でいえば、
成果が楽にでるかどうかがわかるとこまでは、
多数のサービスを展開したほうが、
何に引き続き1点集中すればいいかがわかります。
つまり成果が楽にでるかどうかがわかるとこまでの展開は1点集中なんだが、
同時か順次多数のサービスも分散して展開していったほうが、
成果が出るものを見つけるのは早くなるということになります。
一休さんと和尚さんの問答みたいな話になってますが、
1点集中で成果を出しやすくするには、
1点集中で楽に成果が出やすいものを1点集中で
複数展開してみることも必要ってことですね。
この場合は「ビジネスは分散化したほうが良い。」
という表現になります。
2、収益逓減の法則という話。
次に収益逓減の法則が「1点集中」を万能にしてくれません。
どういうことかというと、
ビジネスって、ある規模までは少ないリソースで利益が大きくなっても、
その規模以上にしようとすると、
それまでの何倍もリソースが必要になるという性質があるということです。
たとえば、オンライン日本語レッスンサービスを展開したとします。
小さい広告費、単純なマーケティングで月額支払い顧客増えたとして、
150名の顧客まで増えたとします。
そうするとその顧客数を超えたあたりから、
急に集客が鈍化したりすることがあります。
同じことをしていても顧客が増えず、頭打ちするんです。
これまで1顧客を5000円で獲得できていたのに、
さらに増やそうと思うと15000円かかってしまう。
とか、
これまで順調に先生をリクルートできていたのに、
これ以上の人数を抱えると急に応募が集まらなくなってくる。
こう説明するとわかりやすいですかね?
この場合は「1点集中=今のサービス」では、
楽に収益が増やせているとは言えません。
1点集中がかえってデメリットになってしまうんですね。
となると、やはりもう1つ別の「楽に収益が出やすい。」サービスを
手がけるほうが収益を増やすという意味においては合理的です。
今のビジネスをスタッフなどで仕組み化しつつ、
新しいサービスをまた「1点集中」で立ち上げていくほうが
収益は楽に伸びていきます。
この場合も分散化したほうがいいことになります。
3、トレンド変化の速度が尋常じゃない。
今ECサービスを展開している会社では、
多品目、多カテゴリ、多店舗の展開が主流になっています。
たとえば日本で最年少上場して著名な「Yutori社」は、
アパレルブランドを展開する会社でありながら、
最初から多くのブランドを同時に展開しています。
社長さん曰く「今はブランドの寿命が異常に短い。
だからコンセプトは守りつつ多くのブランドを同時に展開して行く必要がある。」
といったことをおっしゃっていました。
また日米ともに何かのカテゴリ、
たとえばインテリアなり、ファッションなり、工具で成長したECも、
今は他のカテゴリの商品をどんどん増やし、
さらにマーケットプレイスといって自社仕入れ以外に
プラットフォームとして品目数をとにかく増やしています。
実際アメリカでも日本でも小売で勢いがあるのは、
数多くの品目を扱うドンキホーテや、
食品から薬、化粧品まで扱うドラッグストアです。
僕らのクライアントさんでも、
多品目の転売を行う方は、
化粧品から電化製品、おもちゃまで扱い、
さらに日本向け以外に、アメリカ、ドイツ、オーストラリア向けと
複数展開しています。
サービス業でもその事例はどんどん増えていますね。
もちろん収益逓減の法則によるところもあるのですが、
やはり時流や政治的な変化、パンデミック、戦争などなど
ビジネスの環境が変わる速度が早いので、
そのリスクヘッジって意味も大きいと思うんですね。
1つのサービスとかマーケットが、
ダメになる速度が早くなってるわけです。
これはリソースがどうとか言ってる場合ではなく、
外部要因として多数展開しておかないと生き延びれないってことになるわけです。
■分散する場合は「強み」を軸にする
ここまでで、1点集中は必要だけど、
その次は分散や他サービス展開が必要になることもあると話したわけですが、
とはいえ、とにかく分散すれば良いってことでもないんです。
それは、やはり僕らが「弱者」だから。
すでに強者になってるならなんでもやればいいのでしょうが、
弱者である限り、限りあるリソースを最大限使わなければ成果が出せない。
ことに変わりありません。
そこで大事なポイントは「強み」「コアコンピタンス」を
軸にするということです。
とはいっても、
「自分の強みを活かせ。」というような、
社長個人の資質の話ではありません。
どういうことかというと、
何かのビジネスを1点集中で立ち上げて利益を出している場合、
そのビジネスをやってるという「強み」が存在しています。
「ノウハウ」「慣れ」と言ってもいいかもしれません。
そしてスタッフもそのビジネスにチューニングされてます。
ECをしてれば、商品登録や、受発注、CSといったことに
最適化される組織になってるってことです。
スクール事業をしてれば、
動画編集や、広告調整、カスタマーサポートみたいなことに
慣れてる組織になってるはずなんですね。
なにより、オーナーがその事業で何をすれば金になるかを
肌感でもわかってたりします。
新規のサービスを行う場合でも、
これがそのまま活かせる方がいいってことなんです。
具体的に言えば、
僕の会社は海外在住の方むけのビジネスコンサルサービスですが、
コンサルティングスキルやノウハウ、
顧客対応ノウハウ
海外在住者さんのネットワークやマーケットの把握
という経験を軸にするべきなんです。
日本人向けのコンサルサービスや、
海外在住向けのライフコーチサービス
海外在住者向けにマーケティングスタッフの派遣サービスをするなら、
どっちにも強みはスライドできると思うんですね。
ですが、株式投資スクールとかになると
コアなところがあまり活かせません。
楽に収益化できるということを目指すなら、
やはりコアコンピタンスを軸にビジネスを選ぶべきなんですね。
イタリアのクライアントさんは、
もともとはプライベートガイドからスタートしたのですが、
イタリア国内に知己が多く、
国内事情に精通していることや、
日本から来る日本人のお世話をするという経験をスライドさせて、
イタリア現地通訳
イタリアブライダルコーディネート
イタリア留学
とサービスを展開していきました。
当然リスクヘッジと収益逓減などすべてが理由です。
アメリカのクライアントさんは、
アートメイクサロンを自国で経営していて、
その後日本向けにアートメイクスクールを展開し、
次に国内でアートメイククリニックの運営を始めています。
もちろん、できるなら全然違う畑のビジネスでもいいのですが、
やはり限られたリソースで楽に収益を上げるというセオリーからは外れるので
できれば今すでに収益化に成功した「経験」「ノウハウ」といったものを
使えるとより効果的かなと思います。
■まとめ
いかがですか?
「結局どっちだよ!」って話に聞こえたかもしれませんが、
すいません。「どっちも」なんです。
立ち上げは1点集中で絶対やるのだけど、
楽に収益化するものを探すという初期段階では複数やるべきです。
楽に収益がでるものがみつかったら、
それ1点に絞って拡大していくべきです。
でも、どこかで収益逓減にぶつかるだろうし、
時流も変わるので、
その時は分散して別のサービスを展開するべきです。
世の成功企業も概ね他展開多品目になってきいます。
ただし「強み」を必ず使わないと楽に収益が出にくいです。
ということなんです。
さて、今のあなたはどうか?
一度振り返ってみてください。
では。
※もし自分のビジネスについて相談したい場合はこちらからどうぞ。
無料相談のご予約はこちらから
▼
https://www.contentslab.net/ppc_new.html
【雑談】未来と過去どっちに行きたい?
息子とこんな話をしてました。
未来と過去に行けるとしたらどっちに行きたい?
よくある話だけど、
これ人によって意見が違っていて聞くと面白いです。
自分が生きてる範囲って条件があるかどうかでも変わると思いますが、
彼は、
「自分の生きてる範囲なら未来は今から見れるから、過去がもう一度見たい。」
「年代関係ないなら自分は見ることができないから未来が見たい。」
って言ってました。
好奇心とか感情的なことが優先されてるんですよね。
僕は全く逆で、
「自分の生きてる範囲なら未来を見て、今からの行動に生かして得したい。」
って夢も希望もないことを思ってました。(笑)
でも「年代関係ないなら、探究心で歴史を見てみたい。」
こっちは感情面が優先されましたけどね。
どうでもいいことですが、
あなたはどうですか?