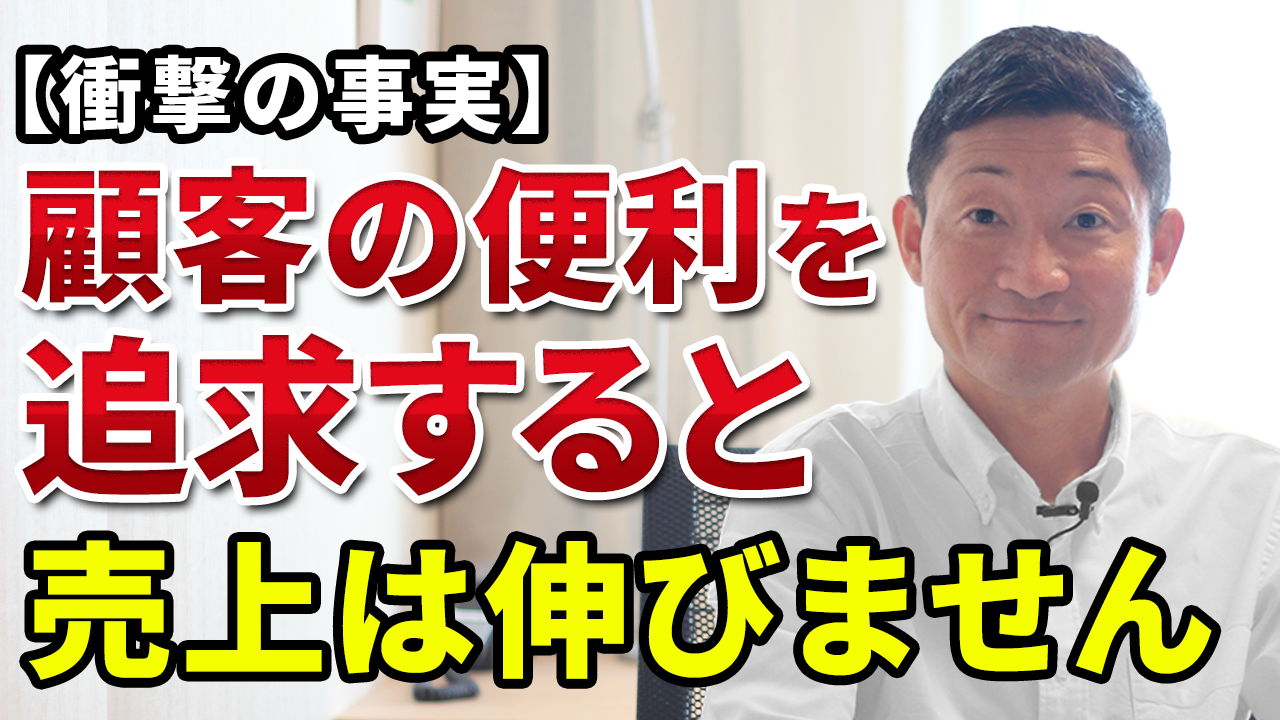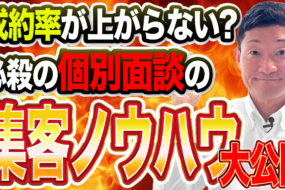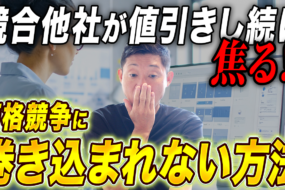【売上アップ法】顧客の便利を追求すると売れない?2025年の可処分時間争奪戦の勝ち方
 日本河野竜夫
日本河野竜夫目次
「顧客の役に立つことを提供すると、
逆に売れなくなるのはご存知ですか?」
ビジネスで成果を出す秘訣には、
時代が変わっても変わらない「普遍的なもの」と、
時代によって大きく変わっていく「変化するもの」があります。
僕はどちらかといえば「普遍的な話」をすることが多いですが、
今日は、無視できないくらい重要な“時代の変化”について話します。
知らない人には結構衝撃かもしれませんし、
薄々この変化に気がついている人にとっては、
答えがやっとわかることになると思います。
2025年の今。
これについていけないと、
これからのビジネスはかなり厳しくなるのではないかと。
その大きな変化とは、
「顧客の役に立つことをする」
「顧客が求めていることを提供する」
「利便性を最大限に上げる」
この“王道”をそのままやっていると
売れなくなってきている。
ということです。
にわかにには信じがたいんですが事実です。
なぜそんなことが起きているのか?
今日は順を追って説明しますね。
nbsp;
動画で見る|顧客の便利を追求すると売れない?
文章バージョン続き|顧客の便利を追求すると売れない?
この話をする前に、まず押さえておきたいキーワードがあります。
それが「可処分時間の奪い合い」です。
■可処分時間の奪い合い
可処分時間とは生活に必要な時間(睡眠・食事)を除いた、
自由に使える時間のことです。
エンタメや嗜好品の業界では昔から、
この時間を「いかに奪うか?」がテーマでした。
可処分時間を自社の商品に使ってもらえば
それだけ売上が増えるからです。
例えば、昔から電車に乗ってる時間は手持ち無沙汰なものです。
まさに可処分時間。
この時間を、漫画、雑誌、文庫本が奪い合っていました。
夜の在宅時間は、テレビとラジオ、ビデオゲームが戦い、
休日はゲームセンターとカラオケが戦うみたいなかんじで、
消費者の限られた時間を奪い合っていたわけです。
■スマホで激化した時間争奪戦
この可処分時間の奪い合いは、
携帯からスマホの登場で一気に激化しました。
スマホは、これまでと違って
シチュエーションを選ばずに手軽に可処分時間を投入できます。
すべてを投入できるくらいの機能があります。
その結果人はほっておくと、
スマホで可処分時間を使うようになりました。
楽ですからね。
結果ほほとんどのエンタメサービスは、
スマホで消費される可処分時間を、
いかに先に長時間抑えてしまえるかを
重視するようになりました。
だからNetflixは次のエピソードを自動再生し、
TikTokが流行ればInstagramがリールで追随する。
こうして「浮気させない仕組み」がどんどん進化していきました。
逆にスマホ上の可処分時間を使って提供できない
カラオケなどもスマホの時間をいかに奪うか?
みたな発想が必要になっていきます。
■ビジネスもエンタメ化
とはいえ、
これまで僕たちスモールビジネスオーナーが扱うような商材は、
エンタメではないことが多かったと思います。
ニーズ商品のネットショップ
ダイエット関連
ビジネスや起業支援
コーチング
自己啓発
etc
これらは目的達成のために”必要とされている”ものであって、
可処分時間を消費するような類ではありません。
時間が意図して確保して投下されるもので、
“娯楽”とは違う領域です。
しかしこの数年でこれらの分野までもが、
エンタメ化してきています。
そう感じませんか?
人気のビジネス系YouTuberや
人気のコンテンツも、
ずいぶんライトになったと思うんです。
これには2つの側面があると思います。
一つは、昔ながらの暇な時間ではない時間も、
スマホでの可処分時間の消費が激しすぎて、
ビジネスやスキルアップ、自己実現のような時間も、
NetflixやInstagramのリールと同じ土俵で
「時間の奪い合い」をするしかなくなってしまった点。
もう一つは、そもそもすべてのサービスがエンタメ化している
と言う点です。
ニワトリが先か、卵が先かみたいな話ですが、
わかっていることは、
すべてのサービスが可処分時間の奪い合いのゲームに
参加するしかないということなんです。
■従来型のオンライン施策が効きにくくなった
と、ここまでが今日のテーマの前提となる
背景理解です。
この背景が影響したことで、
「顧客の役に立つことをやると売れない。」
という信じがたいことが起こってるわけです。
ではここからは本題の説明をしていきます。
まずはオンラインビジネスにおける、
マーケティングの従来の方法について復習してみます。
オンラインで顧客獲得を効率的に行う王道の流れといえば、
まず見込み客が興味を持ちそうな動画やPDF(ホワイトペーパー)を配る。
その後メルマガで教育啓蒙を行い信頼を獲得し、
頃合いを見てセールスメールを送り、
秀逸なコピーライティングを施したLPで、
有料サービスに申し込んでもらう。
こういったものです。
このプロセスで特徴的なのは、
顧客との接触が「非同期」になってることなんですね。
こちらの発する広告でも配った動画も資料も、
メルマガも顧客の都合の良い時間と場所で
見てもらえれば良いものになってます。
だって、それがネットの最大のメリットだし、
顧客だって忙しいんだから、それが良いはずです。
しかし今、これがどんどん効きにくくなっています。
理由のひとつには、
コロナ後にほぼすべての企業がオンラインマーケティングにシフトし、
顧客の情報接触が飽和してしまったことがあります。
が、もう一つの理由の方がとても重要。
顧客に時間の使い方を委ねる非同期の接触(PDF・メール・動画)が、
他のコンテンツに可処分時間を奪われてしまっていることで、
実現できなくなってるということです。
スマホで激しく可処分時間を使ってしまってることで、
僕らのコンテンツは1行も1分も見てくれないんです。
■接触回数と時間が信頼を作る
ここで問題が起こります。
ビジネスでは顧客に信頼してもらうことが
何より重要です。
そしてその信頼を作るのは、
品質以前に「接触回数」と「接触時間」です。
これは心理学でも“ザイオンス効果”という有名な原理で
論じられています。
「繰り返し接触するほど相手への好意や信頼が高まりやすい。」
ということです。
ところが今、非同期の接触方法を使うと、
可処分時間の争奪戦に負けて、
この接触を確保できない可能性が高いです。
顧客の利便性を考えれば、
自由に時間を使ってもらえるのがいいに決まってるのですが
これが逆効果になってるわけです。
だってエンタメサービスではないのだから、
可処分時間を奪えるほど、
強烈な刺激は与えられませんよね?
これがものすごく大きな変化です。
ではどうするか?
必要になるのが、
可処分時間を確実に確保できる接触方法です。
■時間を確保する方法
顧客の可処分時間を確実に奪う工夫が必要だといっても、
刺激や反射ではサービスの性質上与えられません。
詐欺まがいの射幸心や恐怖を与えればできなくもないですが、
それはそれでリスクがあります。
なので残る手段は1個。
せめて接触する時間を「同期させること」です。
乱暴に言えば電話営業や個別相談。
マンツーマンの対話、ライブセミナーや体験会などです。
これらの最大の効果は、
顧客の可処分時間を予約という形で確保できること。
可処分時間を自由に選択するんじゃなくて、
予約しちゃう感じですね。
その時間で品質を証明し信頼を築けます。
実際、僕のクライアントや自社でも、
この2年ほどライブ説明会や個別相談を強化した結果、
非同期の接触よりも明らかに成果が上がっています。
■全分野が同じ戦場になった。政治も?
スマホ登場から可処分時間の奪い合いは常識でしたが、
以前はビジネスや自己成長系など
「浪費時間と思われにくい分野」は除外されていました。
しかしその境界は、
今や完全になくなっていると感じます。
余談ですが、先日日本で国政選挙がありました。
政治活動に多くの人が参加し盛り上がっていましたが、
これも政治がある意味エンタメ化し、
可処分時間の奪い合いに成功した結果とも言えます。
本来は自己啓発や占いサービスに没頭して金と時間を使う人が、
政治の応援活動や寄付に可処分時間を使っていたのではないかと思うんですね。
■ビーチでバカンスしながらチャリンチャリン?
ここまで理屈で説明してきたつもりですが、
まだにわかに信じがたいですよね?
顧客にとって時間を制約されるのは不便なはずです。
わざわざどこかに行くのも面倒ですし、
インターネットの最大のメリットは「時間と場所の制約がないこと」ですから。
でもその方が売れるのは事実なんです。
昔からオンライン的なビジネスに参入する場合、
目指すゴールは「自動的な収益源」というのが定説でした。
ビーチでバカンスしながらチャリンチャリン、というやつです。
『週4時間だけ働く』という本がベストセラーになったのもその象徴。
もちろん、組織化すれば今でも実現可能ですが、
それはもはやインターネット的というより「経営論」の領域です。
すくなくても、売上の増やし方という文脈では、
このあたりの「自動的に」は通用しなくなってきています。
変わったからですね。
ポジティブに言えば、
いまだにオンライン、自動化を目指す人を尻目に、
「リアルタイム性」「同期型」の要素を取り入れれば、
効率的に売上を増やせるようになりました。
いかがですか?
ここまでが、
「顧客の便利を追求するとモノが売れない」
というカラクリです。
ぜひ面倒がらずにライブや個別相談など、
同期した時間を過ごせる仕掛けを取り入れてみてください。
それこそが、今のインターネット的ビジネスにおいて有効な戦い方です。
ちなみに僕はこの状態を、
「昭和に戻った。」と説明しています。
ぜひこの昭和の時代を
上手に生き延びていきましょう。
※もし自分のビジネスについて相談したい場合はこちらからどうぞ。
無料相談のご予約はこちらから
▼
https://www.contentslab.net/ppc_new.html
【雑談】タイで起業した熱い話
「マッドユニコーン」が面白いです。
最近Netflixで配信中のタイドラマ
「マッドユニコーン」が面白すぎてひさしぶりに一気見しました。
実在のタイのユニコーン企業をモデルにした
起業物語です。
ちなみにユニコーン企業というのは、
創業10年以内で時価総額が10億ドル(約1,500億円)を超える未上場企業のこと。
数が少なく希少価値が高いことから、
空想の生き物ユニコーンになぞらえてそう呼ばれます。
テーマは要するに起業です。
物語は貧しい若者がアイデアと根性で起業し、
仲間を集め、困難の連続に立ち向かいながら
巨大企業の嫌がらせとも戦うって熱い展開です。
優秀なエンジニアを口説いたり、
資金難で綱渡したり、
社内の裏切りがあったり、
ライバル企業にアイデアを盗まれたり。
「シリコンバレー」や
起業の話が好きな人は間違いなくハマります。
全7話と見やすいのも魅力。
で、驚いたのは主人公が中国語を話せることで、
大きなビジネスチャンスを得たり、
中国人も仲間に引き入れることで
中国語とタイ語が混じった会話で物語が進む点です。
そして提携先も中国企業。
これ、スポンサーの意向ではなく、
モデルとなった企業もアジア展開の中で、
たとえば日本や韓国よりも中国との接点のほうが現実的で、
リアリティが作品にも反映されているそうです。
これも時代ですね。
アジアのビジネスの中心はやっぱり中国。
俳優陣も素晴らしく、
タイの俳優さんたちの演技力に引き込まれます。
エンタメとしても最高だし
タイのこともいろいろわかって面白いです。
ま。見ているとリスクを取る主人公たちが羨ましく思ったり、
「自分は最高に甘い環境にいるななー」と思わされますが(笑)、
それもまたよい刺激になりました。
ぜひご覧あれ。