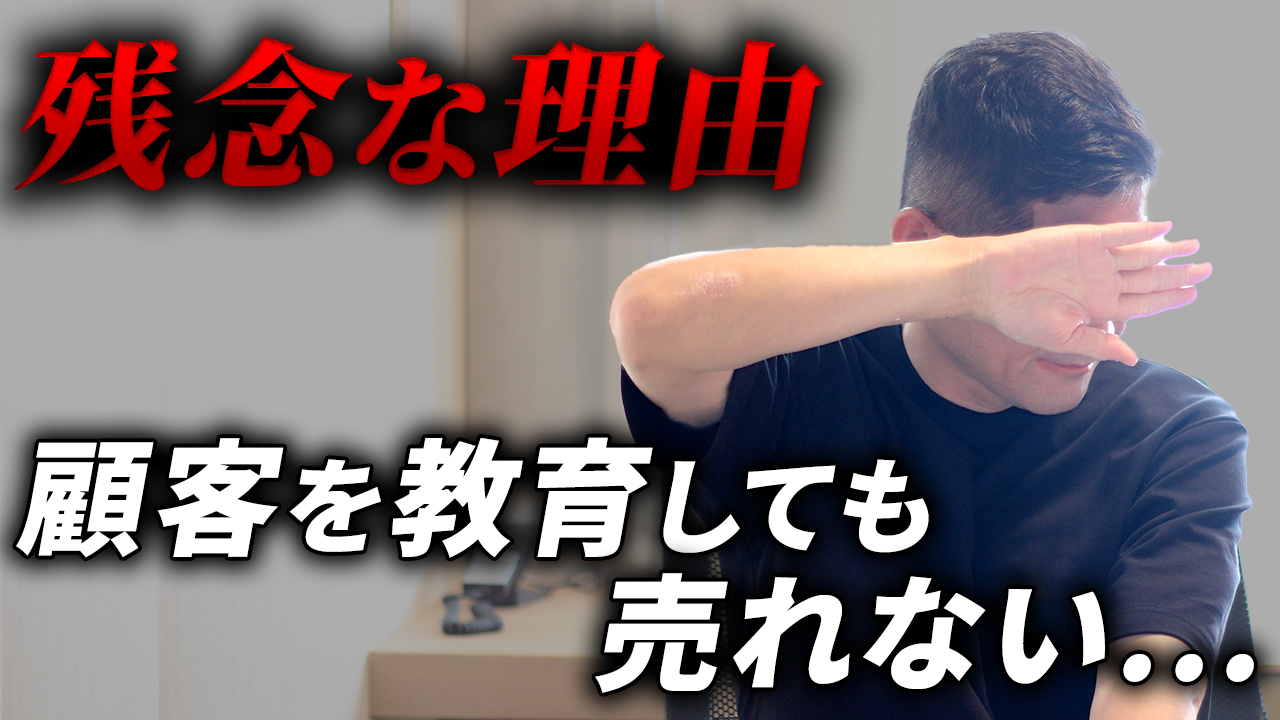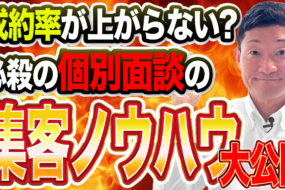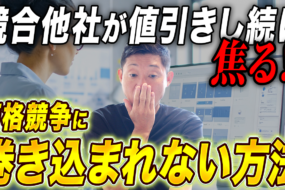【危険】顧客の思考のステージを間違うと売れません。
 日本河野竜夫
日本河野竜夫目次
「顧客を教育すれば売れる。」
「顧客を教育せよ。」
マーケティング業界ではすでに常識になっていますよね。
メルマガやLINE配信、SNSで情報を発信し、
見込み客を「購入するよう育て」てから商品やサービスを売るという、
王道と言われる手法です。
いくら個人ブランドの時代だとか、
AIの時代だとか言われても未だ有効な手段です。
でも、「教育する」ということについて、
実はあまりわからずに見よう見まねで実行してる人や、
何を「教育」したらいいかピンとこないので、
「教育」できてない人も多くいるのではないでしょうか?
僕もダイレクトマーケティングのことを実践し始めた頃は、
「教育」が大事だとわかりつつも、
何を伝えればいいのか感覚的にやっていたところがありました。
見込み客の知りたいことを整理して教えてあげたり、
自分のサービスの良さを伝えてみたり、
こういうことが教育だと思っていたわけです。
つまり、それっぽいメルマガを送ればいいんでしょ?
ってあたりで思考が止まってたんですよね。
でも、顧客の教育ってその人が扱ってるサービスの内容によって、
最適なものが違います。
これを間違うと、教育しても何一つ売れなかったりします。
逆にこれがわかってくると、ものすごく威力を発揮します。
特にメルマガやSNSのコンテンツ発信は労力を使うので、
報われないとしんどいですよね。
ということで今日は、
意外と語られにくい「私は何を顧客に教育すればいいの?」をお話します。
動画で見る|顧客の思考のステージを間違うと売れません。
文章バージョン続き|顧客の思考のステージを間違うと売れません。
まず、前提としてお話しておきたいことがあります。
「顧客を教育しても売れない」と僕は言いましたが、
それはあくまで「効果的に、高い確率で」売れないという意味です。
そもそも、メルマガやSNSで何度も接触すること自体には意味があります。
これは「ザイオンス効果」といって、
人は何度も目にしたり耳にしたりするものを信頼しやすくなるからです。
この効果のおかげで、たとえ「教育」が間違っていても、
接触し続けているだけで売れることはあります。
だからこそ、コンテンツ発信は続けるべきですから、
やらないという選択肢だけは絶対にやめてくださいね。
■何を教育するかは、「顧客の思考ステージ」で決まる
では、効果的に売るために、何を教育すべきか?
それは、見込み客が『問題についてどういう認識でいるか』
つまり『顧客の思考ステージ』を理解することから始まります。
このたった一つの視点が、
あなたのコンテンツを『無駄な努力』から
『成果に直結する資産』に変えるポイントになります。
顧客の思考ステージは、大きく3つに分類できます。
ステージA:問題は知っているが、解決策を知らない顧客
この層は、ダイエットの例でいうと「痩せたい」「体重が増えてきた」と問題は認識していますが、
「何をすれば痩せるのか?」「どんなダイエット法があるのか?」はまだ知りません。
「ダイエット方法」と検索したり、YouTubeで筋トレ動画を眺めたりしている段階です。
ステージB:問題も解決策も知っており、決めている顧客
この層は、「痩せるにはパーソナルトレーニングが一番だ」「糖尿病対策には薬の自費処方が必要だ」など、
問題と解決策の両方をすでに認識しています。
「〇〇(駅名) パーソナルトレーニング」と検索し、複数のジムを比較検討している段階です。
ステージC:問題自体を知らない顧客
この層は、「太ってきたけど、まだ問題ない」と考えている人です。
このままだと健康上の問題があるかもしれないのに、自分に問題があるとは認識していません。
ダイエットや健康に関する情報は、彼らにとってはただのノイズになってしまいます。
わかりやすく英語学習に置き換えてみましょう。
「英語を話せるようになりたいけど、何から始めればいいか分からない」と
検索している人はステージA。
一方、「オンライン英会話のレッスン数を増やすのが解決策だ」と決めて比較検討している人はステージBです。
「日本語だけで十分」と考えている人はステージCです。
このようにあなたの見込み客がどの思考ステージにいるかによって、
教育の方法を根本から変えなければなりません。
■思考ステージを間違うと、教育は意味をなさない。
たとえば、あなたが英語コーチングのサービスをしていたとしましょう。
もし見込み客がステージBの人だとします。
彼らはすでに「英語コーチング」という解決策を知っています。
この人たちに、ステージCの人向けの「英語がいかに必要か?」なんて教育をしても響きません。
彼らが知りたいのは、なぜあなたのコーチングを選ぶべきかです。
選定基準が「メソッド」なら、自分のメソッドを説明する方がよいし、
もし「信頼」なら、受講生の成功例を大量に集めるほうが効果的です。
では、見込み客がステージAの場合はどうでしょうか?
この人たちには、そもそも「個別のコーチが必要だ」という教育を配信すべきです。
この英語学習の例はわかりやすいので、
あまり間違う人もいないかもしれません。
他によくある勘違いの例も出してみますね。
見込み客に完全にステージBの人しかいないのに、
永遠に解決策を教えてあげてるケースなんかがよくあります。
僕が昔、オーダースーツのECをやっていたときの話です。
会員登録した見込み客は、
すでに「いい生地のスーツをジャストサイズで着たい」という問題を
「オーダースーツを買う」という解決策で解決できると決めていました。
完全に思考ステージはBです。
だから、いかに機能的で品質の良い生地が選べるか?
セールでお得に買えるか?保証はどこまであるか?といったことを「教育」するべきだったのですが、
当時の僕は「できる男の着こなし術」なんてコンテンツを作っていました。
すると、まったく売れなかったんです。
しかし、教育の内容をステージに合わせて変えた途端、
メルマガからものすごい成果が出始めました。
完全に思考ステージがBの人に「必要性」なんて教育をすると、
本当に売れませんので気をつけなければなりません。
もちろん、見込み客の中に1種類の思考ステージの人しかいないわけではありません。
複数の層にアプローチする場合は、
それぞれのニーズに合わせてコンテンツをミックスする必要があります。
■というか、ステージAの顧客は難しい。
ここまで聞くと思考ステージがAの人の方が売りやすそうに感じませんか?
つまり問題が分かって解決策が分からない人のほうが売れそうに見えますよね?
まだ無垢な人を意のままに「育て」ることができるからです。
でも、実はめちゃくちゃ難しいです。
なぜなら、あなたの見込み客の大部分がステージAである場合、
あなたの提案する解決策が同じ問題でステージBにいる人の解決策とは異なる場合が多いからです。
わかりにくいんで例を出しますね。
たとえば、英語を学びたい人で思考ステージがAの人に「英語コーチング」を勧めるのは簡単です。
なぜなら、すでにBにいる人も他にいるので、
Aの人もコーチングを選ぶことへの抵抗が少ないからです。
しかし、もし英語を学びたい人へステージBの人が選ぶ解決策には存在しない
未知の解決策を提案したらどうでしょう?
たとえば、「食事で英語を学ぶ、毎週届くレシピを英語で理解して料理を作ろう」
といったサービスだとします。
英語を学びたいという問題はわかってるが、
解決策がわからない人へ食事で英語を学んで解決するべきだ」
と教育するということになります。
「食事で英語を学ぶことがいかに必要か」を説得しなければなりませんが、
この「説得」は非常に骨が折れる作業です。
これは顧客が欲しいと思うサービスを調整する作業、
いわゆるプロダクトマーケットフィットと呼ばれるものなんですが、
ステージAの人を相手にする場合、これが果たせないことが多いのです。
だからこそ、もし思考ステージがAの見込み客を集めて教育するとしても、
その問題意識を持ってるすべての人の中にステージBとしてあなたの提供するサービスが解決策だと
決めてる人が少なくても30%くらいはいるサービスを選ぶべきです。
何度もいいますが、教育しても説得ができない可能性が高いからなんです。
■顧客の思考ステージは商材選びやコピーでも意識するべき
もうお気づきだと思いますが、
ここまでお話したことは教育だけではなく
商材選びやLPのコピーライティングにも言えることです。
顧客の思考ステージを意識していないコピーは、
論理が飛躍し、意味不明になっていることも多いので気をつけたいところです。
たとえば、ヘッドラインで
「英語コーチングを探しているなら私たちにお任せ」と書いているのに、
本文が「あなたが英語スキルをあげたいなら、レッスンを受けてはいけません」と続くと、
前半と後半で対象のステージがずれてしまうのです。
前半では解決策を知ってるBへ向けてるのに、
本文がステージAの人向けになってますよね。
■まとめ
話を戻します。
このように「教育」は顧客の思考ステージごとに、
何を言えば買ってくれるか?を考えて伝えてみて欲しいのです。
語学スクールをしていて見込み客がステージAである場合に「1分単語講座」を配信しても響きません。
でも、見込み客がステージBの場合は、自分たちのコンテンツが優れていることを教育するために
一部抜粋という形で「1分単語講座」を配信するのは有効です。
ハンドメイドアクセサリーのECなら、
もう買いたい人なんだから新商品とセール情報だけでいいと思います。
ちなみに何かを売り込まれている時も、
これがどの思考ステージを対象にしているのか?
という目線で見ると面白いですよ?
例えば流行りのAI系のスクールは、
おそらくステージAの人を対象にしていることが多いはずです。
だから
「何かで稼ぎたい? ならAIスクールです。」
「AIで何かしたい? ならこれ」
という広い訴求をしてるんだろうな。という読みですね。
いかがでしたでしょうか?
いろいろ言いましたので余計混乱した人もいるかもしれません。
でも、「教育を意図した発信」そのものは止めないでくださいね。
冒頭で言った通り、ザイオンス効果でコンテンツを全く送らないよりは全然効果がないということはありませんから。
では。
※もし自分のビジネスについて相談したい場合はこちらからどうぞ。
無料相談のご予約はこちらから
▼
https://www.contentslab.net/ppc_new.html
【雑談】良い酒、良い服、良い車、良い女。
最近、友人がこんな話をしてました。
「綺麗な服を着て、海外の高級リゾート地で集まって、
良い服を着て、良い酒と良い飯を食べる。
そして恋もあったりするコミュニティがあって、
それに知人が参加してて楽しそう。」
友人の友人の話だから本人は存じ上げませんし、
まあ、楽しいならそれが一番て思ったんですが、
同時にふとある映画のワンシーンが頭に浮かびました。
それが有名な映画『スカーフェイス』。
アル・パチーノが扮するキューバからアメリカへの貧乏な移民が、
成り上がっていくギャングの話なんですけど、
そんな主人公がビックになって成功した後で、
高級クラブで酒を飲んでるシーンでこんなセリフがあります。
「俺は成功した。でも毎日良い酒、良い服、良い車、良い女。それだけだ。」
うまい飯 酒 女 でパーティーみたいなの僕の価値観にはないけど
それでも価値は人それぞれだし、
人の価値観にいちゃもんつけてくるやつは豆腐に頭ぶつけてくたばっちまえと思うものの、
自分を省みると、金が欲しい。とは常に思ってきたものの、
その根底には好きなことをしていたい。誰にも理不尽に従いたくない。というのがあったわけで、
自分に刺激が得られる『したいこと』が明確にあってよかったなとも思ったんです。
何が刺激か?と後天的に考える必要がないのは、
実はすごい幸せなことなのかなと。
ま、こう省みるのはただ単に老けただけなのかもしれないし、
今20代で起業してるなら「いえーい!」って言いながら、
酒、飯、女って言ってパーティーしてるかもしれませんけどね(笑)