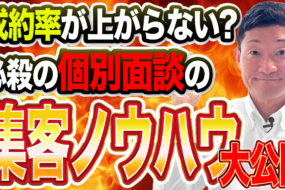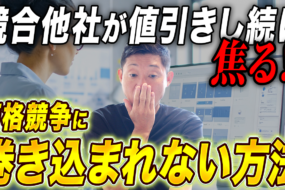AIを使い倒して売上が上がる人・下がる人。その違いとは?創造的意思決定してますか?
 日本河野竜夫
日本河野竜夫目次
僕はとてもとても疲れていました。
体調の話ではありません。
ビジネスの調子が全体的にいまいちで、
なんだか精神的にもしんどかったんです。
笑って話せるけど結構最近の話です。
売上は別に減ってません。
お金も減ってません。
人に裏切られてもいません。
でも、業績が伸びないんです。
サボってませんでしたし、いろんなことをしてました。
が、やることなすこと上手くいかないし、
「何もかもうまくいってないな。」って感覚なんですよね。
僕はこういう人も支援する仕事です。
「は?お前が落ちててどうすんねん。」と突っ込みつつ
原因を調べてました。
それこそあらゆるデータを出して、
分析にAIも駆使しました。
でもやっぱりわからなかったんです。
しっかりデータを揃えて、
AIをフル活用して売上アップの施策を実行しているし、
売上が伸びない時はそのデータをAIに投げて原因を分析して、
対策を講じてきました。
さらにChatGPT,Gemini他、
AIのDeep Researchなんかでも
確認してるのにです。
こんなことは、創業してはじめてでした。
これまで調子が悪いことなんて何度でもあったし、
業績が伸びない、落ちたことも何度もあります。
色々やった結果、全部うまくいかないなんてことも、
テストなんですから当たり前に起こります。
何が違うんだろう?
そこで「はっ!」とあることに気がつきました。
これまでの自分と、その時の自分で決定的に違うことは、
でもAIは効率がはるかに上がるわけですから、
施策の実行速度も上がっている。これが原因とは考えにくい。
だから、まさかと思っていたんですが、、、
冷静に見直した結果、
AIを使い倒しているからこその調子の悪さ・伸びなさだという結論に至りました。
つまり、AIを使ったせいで、売上が伸びなかった。
しかも、成果もメンタルもです。
ちょっと意味わからないと思うんですが、
これ、おそらく多くの人にも起きている気がします。
ということで今日は、
AIを使えば使うほど業績が悪くなる理由と注意点についてお話しします。
動画で見る|AIを使い倒して売上が上がる人・下がる人。その違いとは?創造的意思決定してますか?
文章バージョン続き|AIを使い倒して売上が上がる人・下がる人。その違いとは?創造的意思決定してますか?
AIを使い倒すと、売上が下がる。
この話をする前に、誤解があってはいけないので、
先にAIを使うと業績は本来上がるはずだって話をしますね。
その1番の理由は工数の削減です。
工数の削減には、
時間の削減とコストの削減って2つの視点があります。
時間の削減はいうまでもなく、
・獲得した見込み客リストを自動でデータ化しタグをつける
・見込み客をカテゴリ分けしてセールスメールを自動配信する。
・SNS投稿を自動化する。
・顧客の問合せの返信メールを清書してもらう。
・広告の画像素材をAIに作成してもらう。
・動画編集をAIに代行してもらう。
・データ分析や集計をAIにしてもらう。
・情報収集をAIにやってもらう。
あげればキリがないですが、
こういう細かいけど時間のかかる作業の自動化や、効率化ができます。
また、これらの作業を専門に依頼していたコストを減らせたり、
スタッフの稼働時間を減らせたりすることで経費が減ります。
もちろん「減らす」だけで業績全体(売上)は伸びないのですが、
時間とコストを減らすことで、
その時間とお金が余ることになります。
結果、その時間とお金を使って、
「売上が上がるかもしれない。」施策の、
実行速度が上がったり、
実行できることの幅が増えるので、
業績が伸びていくわけです。
なので本来はAIを使い倒せば倒すほど、
業績は伸びるはずです。
調子がいいはずなんです。
でも1個忘れてはいけないのは、
AIは効率を上げるのであって、
意思決定をしているわけではないのです。
「何を実行するか?」
「何をやめるのか?」
「どのようなものを生み出すのか?」
こういうことはできません。
それをしているように見えることはあっても、
内部構造的にそんなことはしていません。
もちろん僕はこの違いを認識していたのですが、
行動が伴ってなかったんですね。
そのせいで業績が伸びずに、
調子も悪かったんです。
■創造的意思決定と危険回避的意思決定
ここですこし話をわかりやすくするために
「創造的思考での意思決定」というものについて話します。
脳は、創造的思考をする場合に動く場所と、
危険回避をしたい時に動く場所が違うそうです。
当然、ビジネスで業績を伸ばすってことを目指す場合は、
できる限り創造的思考をした上で意思決定をした方がいいと思うんですよね。
なぜなら、自分を俯瞰して、
「どうすれば業績が伸びる可能性があるか?」
「何をするべきか?」
「どんなリスクを負うか?」
と、広い視野で冷静に判断していけるからなんです。
一方、創造的思考においての意思決定と反対語にあたるであろう
危険回避型の思考での意思決定は、
顧客を失わないとか、今の成果を絶対変化させないとか、
絶対お金を減らさないってことを優先した意思決定なので、
どうしても「損したくない」という狭い視野になりがちです。
たとえば、
スタッフをいれなければ人員不足がボトルネックになって、
業績が伸ばしにくいとわかってるとしても、
危険回避型だと、今一人雇っても利益が減ってしまうからできないとか、
その人が使い物になるか?何年も付き合える人か信じられない限り雇えないと判断したりします。
創造的思考の中だと、
どうせ雇わないと始まらないんだからまずは’やとってみよう。
その場合のリスクは再雇用の手間と、その人への教育コストが損失になるだけだ。
やってみるかって判断したりします。
たとえば、
売上が増やしたくて広告予算を上げてみたが、広告の調子が悪い場合、
危険回避型だと、おそらく損をすると思って予算を元に戻すか、
一時的にストップします。
創造的思考の中だと、
この予算で集客できないと業績は伸びないと考えて、
悪化してるものをどう設定を変えたり、
訴求を変えれば成績がよくなるか?と思考錯誤しようとします。
もちろん、僕はこれは理解してます。
できるかぎり創造的思考で意思決定をするように意識してきたんですね。
なんなら作業時間より、
創造的な意思決定をしたという事実のほうが
業績を上げる要因になったという自覚もあります。
(もちろんその意思決定に伴う作業をその後するのが前提ですが)
で、ここで話をAIに戻します。
僕はAIの効果をものすごく感じてますので、
AIを使い倒してる方だとは思うんですが、
それがよくなかったんです。
知らず知らずのうちに、
効率化ではない範囲。
つまり、
「生み出す」
とか、
「意思決定する」
という仕事までAIに頼るようになっていってたんです。
今の現状だと広告はどうするべきか?
これは止めるべきか?増やすべきか?
今後のセールス施策はどんな順序で行うか?
この商品の売れるLPはどんなものか?
語弊があるかもしれませんが、
こんなものLLMのAIに”できるわけ”がないんです。
それっぽいものを、
もっともらしい根拠を添えてアウトプットはしてきます。
ただ、所詮「次にくる言葉は何か?」というシステムである
AIチャットに正解が出せるわけがありません。
でも、AIを使ってると、
「創造的なことも自分よりもAIが正しくできるんではないか?」
と錯覚してしまい、
知らない間に、本当に知らない間に、
答えを出す命令をして、
しかもそれに従うようになっていきます。
まさにこの時の脳のネットワークは、
危険回避型の意思決定なんですよね。
創造的な思考をしてもらおうと、
AIを使うってことそのものが
危険回避型の思考になってるという皮肉だろうなと。
創造的な思考をしてもらおうとAIを使うってことは、
損をしたくないわけです。
重大な意思決定をすることから逃げて、
楽をしたいと言ってもいいかもしれません。
僕の「調子の悪さ」はここにありました。
いつしか創造的な思考そのものをAIに頼っていたのだと思います。
当然、AIが万一創造的な思考っぽいことを提案してることもありますが、
そのリスクや不確実性にビビって、
指示しなおして、
結果危険回避型のアイデアに落ち着かそうとしたりします。
たとえば、自分の現状をAIに投げてどうすればよいか?
って聞いた時に「リスクをとって人を雇え」って言われても、
「それは無理だと思わないか?」みたいなプロンプトを入れてしまうってことです(笑)
で結果、現状維持になるか、
余計悪くなることもあるわけです。
しかも、自分で意思決定してませんので、
焦燥感とか怒りと疲労感とか、そんな感情になります。
もちろん、自分で創造的な意思決定をしたら、
必ず儲かる施策になるなんてことはないのですが、
「自分で決めて責任を持つ」意思決定をするだけで、
納得感はあります。
「あー!ダメだ。次どうしよう!」という感情にはなるとしても、
受け入れてはいると思いますし、悶々とはしないと思うんですね。
てかやはり創造的な思考をしている場合は、
いいアイデアになることのほうが多いです。
こんなふうにAIを使ってると、知らない間に「自分で決めない。」
だから本来は成果を生み出しやすい創造的な思考に慣れないという
悪循環に陥りやすいなと。
僕は自己分析ができてると思ってましたから
創造的な思考のために「AIをクールに使うぜ」って思ったんですよね。
でも汎用的なAIだからこそ、
意思決定を任せようって誘惑にかられてたんだなーって思いました。
■まとめ
まとめると、
AIはあくまで業務効率化とコストカットで使い倒す。
創造的な意思決定に使ってないか何度も自問するべきである。
ってことですね。
なので、
もし、
1、AIにビジネスモデルを考えてもらってる
2、今後の施策について相談している
とかの場合は気をつけてくださいね。
その場合はリサーチに置き換えるといいと思います。
1、AIにビジネスモデルを考えてもらってる
そうじゃなくてこんなふうに指示してみるとか。
▼
同様の業種を10個ピックアップして、
それぞれのビジネスモデルを
価格帯、顧客層、セールス手法などのカテゴリで
分類してみてください。
2、今後の施策について相談している
そうじゃなくてこんなふうに指示してみるとか。
▼
A 施策A
B施策B
C施策C
コストと工数、インパクトの観点から
優先順位をつけるとしたら?
同業他社はどれを優先していると思われるか?
今日はAIを使う場合の切り口でしたが、
やはりどんな意思決定をするか?ってビジネスの拡大にとても重要だと思うんです。
成果を出すってことじゃなくて、
どう決めるか?なんですが、
そこに「自分が間違ってもいいから決める」ってことを
AIのこの時代にはより必要だろうなって話でした。
では。
※もし自分のビジネスについて相談したい場合はこちらからどうぞ。
無料相談のご予約はこちらから
▼
https://www.contentslab.net/ppc_new.html
【雑談】口笛が吹けない一族に生まれた子供たち
僕は口笛が吹けません。
でも50代の今、なぜかたまに練習してます。
もっぱらサーフィンの海の波待ちの時とか。
でも弱点があって、
口笛を練習してる最中に、
いい波がくると、
その波に乗ろうとしているサーファーを煽ってるように聞こえるんです。
海外だとそんなのよくあることなんですが
日本のサーファーはおじさんおばさんも多くみんなおとなしいわけです。
だから後でその人にジロジロ見られたりして気まずいです。
でも、なんだかんだ亀のあゆみですが、
すこし音が出て、たまに音程を出せるようになってきました。
(上達遅っ!)
で、話が変わりますが、
口笛って遺伝するそうです。
口笛が吹けない親の子供も口笛が吹けないんだとか。
なんでも親が吹いてないと、
小さい頃に真似しようともしないので、
結果吹けないんだそうです。
確かに!
うちの子供たちは口笛が吹けないし吹こうともしないんですよね。
でもまだ間に合うかもと思って、
最近は家でも練習するようにしてみました。
でもちょっとでも下手な口笛吹くと、
「うるさい!」と大合唱されて秒殺されます。
我が家の家系は、
やはりこれからも「口笛が吹けない一族」になりそうです。